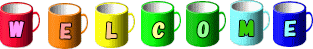
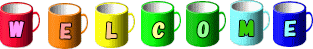
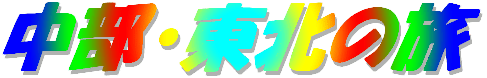
|
|













|
|
初日
.jpg)
.jpg)
.jpg)
今回の旅は日程と時間がたっぷりあるので
なるべく高速道路を使わずに各地を廻る為に
お盆最終日である日曜日の午後に出発。
長野県の松本市内で渋滞にあったが
何とか「大王わさび農園」に到着した
まだまだ混んではいたが
車は最も近い駐車場に停めることが出来た。
大王わさび農園
.jpg)
.jpg)
.jpg)
大昔に来たことがあるが
改めて広大な面積の広さに圧倒された
美味しい山葵を造るには冷たい水が必要で
川を渡って一周して戻ってくるには
結構な時間がかかるので途中で止めた。
多くの観光客は、わさびソフトが目当てなので
売店前には行列が出来ていた。
ゲストハウス
.jpg)
.jpg)
今日の観光はここだけなので
このまま池田町の宿に向かった
値段がお得なゲストハウスだが
綺麗な造りで到着したら、お迎えもしてくれた
汗だくだくになったので早速風呂に入り
同宿人になった人とビールでカンパイした
ただクーラーが無かったので夜は寝苦しかった。
二日目
.jpg)
.jpg)
二日目は黒部ダムの見学から
車を無料の市営駐車場に停めて少し歩く
近くて便利な有料の駐車場は満車である
切符を買ってトロリーバスの出発まで並ぶが
廻りが中国人だらけで大変うるさい
国はインポートに必死だが
日本人旅行者は大迷惑である。
黒部ダム
.jpg)
.jpg)
.jpg)
黒部ダムに到着後が勝負の分かれ道である
220段の階段を登って放水を見るか
そのままダムの堰堤で我慢するかだが
多くの人はフーフー言いながら階段を登る
展望台に着いた時にはしばらく動けない
ただ、この景色を見たら忘れる
黒部の太陽
.jpg)
.jpg)
.jpg)
映画「黒部の太陽」の撮影記念の場所が出来ていた。
たぶんここが黒部第四発電所建設などの
工事用ルートとして整備された
黒部峡谷の欅平から黒部ダムをつなぐ
新ルート「黒部宇奈月キャニオンルート」で
こちから観光客を招き入れる予定だったが
急遽中止になってしまった。
白馬ジャンプ台
.jpg)
.jpg)
.jpg)
黒部ダムで昼まで見学した後は
白馬八方尾根スキー場のジャンプ台を見学
サマージャンプが行われている事を期待していたが
残念ながら飛んでいなかった。
ただ、500円を払えばリフトとエレベータを乗り継ぎ
真下が透けて見える金網の上を歩いていくと
スタート位置まで来ることが出来る。
(男子は金〇がすーとするかも)
長野オリンピック
.jpg)
.jpg)
.jpg)
1998年長野オリンピック団体金メダル。
原田選手の一回目の失敗ジャンプを
皆で取り返したのを見て
ものすごく感動したのを思い出した。
仕事中だったが何故かテレビをライブで見れた
あれから26年もたつのか
岩岳スキー場
.jpg)
.jpg)
昔はマイ・ゲレンデだった岩岳スキー場へ
最近は年齢の為にスキーも止めてしまったので
久しぶりにやってきた。
マウンテンバイクやフィールドアスレチック等で
ものすごく賑わっていたのは驚いた。
今年の冬には新しいゴンドラもオープンする
ただ、何時も泊まっていた宿は見つからなかった。
三日目
.jpg)
.jpg)
.jpg)
夕べは安かろう悪かろうという宿だったので
全く寝れなかった(たぶん)
朝6時に出発、全く行く気が無かった善光寺へ
初めて来たので横の駐車場から入った為に
仁王門まで一度逆走して戻ってきた
力強い仁王像の阿形(あぎょう)吽形(うんぎょう)は
頼もしい番人で高村光雲・米原雲海による作である。
善光寺
.jpg)
.jpg)
.jpg)
創建以来約1400年になる長野市の善光寺
民衆の心の拠り所として篤い信仰を集めている
日本に仏教の宗派が生まれる以前に創建され
無宗派寺院として長きにわたって
すべての人々を受け入れてきたそうだ。
御本尊・一光三尊阿弥陀如来は
人々を極楽浄土の世界へ導くご利益があるとされる。
国道117号線
.jpg)
.jpg)
.jpg)
国道117号線を青い服を着た国家公務員に
お世話にならない様に淡々と走る
そして記念写真を撮られない様に注意して走る。
途中に信濃川展望地なる看板を見つけたので
急ぐ旅ではないので暇つぶしに寄った。
このような場所をボーと眺めているのは
心が癒されるので好きだ。
清津峡
.jpg)
.jpg)
.jpg)
今回の旅で行きたかった場所の一つが
新潟県十日町にある清津峡である
超人気の場所なので繁忙期には整理券が必要だが
お盆過ぎなので大丈夫だった
しかし想像して以上に観光客が多く
駐車場もかろうじて停めることが出来た。
清津峡トンネル
.jpg)
.jpg)
.jpg)
清津峡トンネルを通行するのに千円かかる
駐車場からトンネルまで300m、トンネルの長さが700mあるが
例の外国人達がトンネル内で騒ぐので響いてウルサイ
黒部峡谷(富山県)・大杉谷(三重県)とともに
日本三大峡谷の一つとして知られる「清津峡」は
川を挟んで切り立つ巨大な岩壁が続いて
全国に誇るV字形の大峡谷をなしていて圧巻だ。
小千谷市
.jpg)
.jpg)
.jpg)
自由気ままな旅なので余裕がありすぎて
今晩宿泊する小千谷市には昼過ぎに到着した。
どこも見学するところが無いのでネットで調べて
総合産業会館「サンプラザ」を見に行った
時間にして20分ぐらい居たかな
四尺玉の花火の模型を見て思ったが
いくらぐらいの値段で造れるのか知りたい
錦鯉の里
.jpg)
.jpg)
今度は錦鯉の里を見つけた。
全く興味がないがやることも無い
どうしようか迷ったが見学することにした。
色鮮やかな錦鯉を見ているうちに
何故か田中角栄元首相を思い出した
もう少し距離を稼いで北まで行けば良かった。
ゲストハウス「平成イン」
.jpg)
.jpg)
.jpg)
早くもゲストハウスに向かう
場所は街中にあって非常に解り難かった
予約は値段の都合で相部屋だったが
一人部屋が用意してあった
しかも滅茶苦茶新しく綺麗で広かった。
たまった服等をランドリーして
入浴後に美味しいビールを飲みながらご飯を食べる
至福のひと時を過ごした。(シ・ア・ワ・セ)
四日目
.jpg)
.jpg)
朝6時30分出発
一日をかけて鶴岡市まで行く予定を組んでいるが
新潟亀田のオカモト石油でガソリン補給するだけで
見学する場所が無い為に時間が余り過ぎた
道の駅「新潟ふるさと村」で休憩
オープン前なので地図を眺め今後の予定を確認
次回の東北の旅はもっと距離が稼げるようにしたい
羽州浜街道
.jpg)
.jpg)
.jpg)
このまま日本海を見ながら行くか
山形市経由で月山の噴水を見て行くか迷っていた
順調に道路を走れるので時間が早すぎるも
今まで陸地を見ながら来たので
左に粟島を眺めながら潮風を切ってドライブした
そしてまたまた道の駅で長い事休憩を取る
木陰に入れば爽やかな海風が吹いているので有難い
おけさおばこライン
.jpg)
.jpg)
.jpg)
爽快な羽州浜街道(おけさおばこライン)を走る
余りキョキョロ見ながら走ると危ないが
ついつい初めての道なので景色に見とれてしまう
途中停車しながら日本海を見て深呼吸する
脳に新鮮な空気を入れないと眠たくなってくる
ゲストハウス「わたうさぎ」
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Booking.comで宿を取ると欠点があり
電話番号が無い為にカーナビで設定が出来ない
スマフォのGoogle Mapsを利用しないと
解りにくて宿までたどり着けないのが難点だ。
今日も早く午後三時にゲストハウスに到着
部屋は改装したばかりで綺麗だったが
基本が電車旅が多いのか?駐車場の狭さには参った。
五日目
.jpg)
.jpg)
宿を朝6時に出て国道7号線を走り
最近知ったばかりの十六羅漢を目指す
片側二車線のバイパスになっているので
時速換算で75Kmぐらいのスピードで走っている
その時こんな朝早くからネズミ捕りをしているではないか
幸いにも前者に続いて走行していたので助かった。
いったいこの国道の設定は何キロだろうか?
十六羅漢駐車場
.jpg)
.jpg)
ユーチューブの東北の旅を見ていたら
ぜひとも見学したかったので寄った
平日で朝早い為に駐車場には誰もいない
何処に行ったらいいのか解らないので
とりあえず海辺に向かったところ
ちゃんと「道しるべ」がしてあるではないか
十六羅漢岩
.jpg)
.jpg)
.jpg)
海禅寺の21代寛海和尚が仏教の隆盛と
事故死した漁師の供養と海上安全を願って
1864年から5年の年月をかけて完成させ
明治元年22体の磨崖仏を完工しました。
十六羅漢に釈迦牟尼、文殊菩薩、普賢菩薩、観音、舎利仏
目蓮の三像を合わせて22体ある
※ただし全部は解らなかった。
鳥海ブルーライン
.jpg)
.jpg)
.jpg)
続いて鳥海ブルーラインを走る
展望台までの登りが15Kmほどあるが
森に囲まれているので景観は良くないし
道路はヘアピンコーナーが続いているので
ドライブしていても楽しくない
展望台からも庄内平野を見下ろせるはずだが
雲が多くて遠くまで見渡せなかったのは残念だ。
白瀬南極記念館
.jpg)
.jpg)
.jpg)
白瀬南極探検隊記念館は是非見たかった場所
17年ぶり二回目だが記憶に残っている
ただし、ここに来るまでの道は
高速道路は無かったし随分変わっていた。
そして家族連れで来た時も
入館料が安かった記憶がある
南極観測隊雪乗車
.jpg)
.jpg)
.jpg)
以前夏休みに来た時も客は少なかったが
残念なことに今日も私一人だった
おかげでゆっくりと見学出来たが何か淋しい
観測隊雪乗車の中も無線機だらけで
基地に連絡するイメージが湧いてきた
南極の氷も触らせてくれたし良い記念になった。
なまはげ像
.jpg)
.jpg)
.jpg)
男鹿半島に入り、なまはげラインを走る
巨大な「なまはげ像」を目当てにしていたので
三度目だが何か嬉しくなってきた。
ウイークデーなので観光客も少なくて
独り占めできるくらいだ
ゆっくりと記念写真を撮る事が出来た。
真山(しんやま)伝承館
.jpg)
.jpg)
時間の関係で先に伝承寸劇を拝見した
三回目なので一番初めに見た時ほど
驚かなくなってきたのはしょうがないかな
しかも普通ならダメだと思うが
なんとスマフォ撮影は許可されていたので
子供たちにラインで送ってやった。
なまはげ館
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
改装されていた「なまはげ館」を見学
館内も広くなっていて展示物も増えていた。
年末になると必ず全国ニュースで放送される
初めて知ったが、なまはげの面も
男鹿半島の各地で微妙に違っていて
真山地区は角が無いのが特徴だそうだ。
入道崎
.jpg)
.jpg)
.jpg)
男鹿半島の先端の入道崎に向かった。
最北端とか最先端と言われる場所が好きなので
車やバイクで旅をしている時は
出来る限り見学に行く事にしている
ここには北緯40度のモニュメントが設置されている
記念写真を撮るのも生き甲斐である。
男鹿半島一周
.jpg)
.jpg)
.jpg)
男鹿半島を一周して宿に行く事にした。
アップダウンとカーブが続いているので
スリリングな気分が楽しめる
途中に水族館があったが興味ないので素通り
逆に、なまはげ像を見つけた時には
通り過ぎたので戻って記念写真を撮った。
ゴジラ岩
.jpg)
.jpg)
.jpg)
ゴジラ岩があることは知っていたが
すっかり忘れていた
今晩の宿のことばかり考えていた時
県道59号線沿いに車が数台停まっていた
野次馬根性が頭をよぎったので見に行くと
ゴジラ岩の看板があるではないか?
解り難い場所にあるが確かにゴジラに見える。
宿「ひるね」
.jpg)
.jpg)
.jpg)
今晩泊まる宿「ひるね」に到着した。
チェックインが無人方式なので解り難い
外国人が目当てなのか、ちょっとムカついた
インバウンドも大事だが
おじさんの客も大事にしてほしい
ただ、一軒宿だったが他には誰も居なくて
貸し切りだったので有難かった。
六日目
.jpg)
.jpg)
通常の旅行の日程を倍にして組んであるので
今日も余裕の行動で好きなだけ見学出来る
この先十年以上会えないと思うので
なまはげ像の横を通った時にやはり寄った
朝早く誰も居ないので好きなポーズで写真を撮った。
働いている時には出来なかった事だが
値段は安いし観光客も少ないので旅は平日に限る
道の駅「五城目」
.jpg)
.jpg)
.jpg)
秋田浪漫街道(国道285号)にある道の駅「五城目」で休憩
ここは車中泊旅で来た時にお世話になった場所である
駐車した車両(ホテルアルファード)の隣の池で
夜中にウシガエルの鳴き声で寝れなかった事等
記憶がばっちり蘇ってきた
それ以外は涼しくて良い思い出が残っている
道の駅「たかのす」
.jpg)
.jpg)
.jpg)
道の駅「たかのす」で一休み
車を停めると大きな太鼓の絵が目に入った
国内唯一の大太鼓の博物館である。
まあ、暇だし当然寄るわな
直径3.8メートル、胴の長さ4.52メートルの大太鼓
驚くことに重さは3.5トンもあるそうだ
世界遺産
.jpg)
.jpg)
ナビに大湯環状列石という世界遺産が出て来た。
東北有数の縄文遺跡と書いてある
普段なら絶対スルーする場所だが今日は違った
あくまでも自己解釈によると
縄文時代に宇宙人が来たという場所だ
ほんまかいな??
しかし今年はどこもクマ注意の看板が多い
発荷峠
.jpg)
.jpg)
.jpg)
やっと発荷峠の到着した。
ここから見る十和田湖の景色は見ごたえがある
ただ少し前にクマが出たとニュースがあったので
ちょっと怖い気がしたのは言うまでも無い
ここに来たのも二十年弱の間が空いているので
綺麗になって展望台も変わっていたし
売店も出来ていたので浦島太郎状態かな
十和田湖へ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
こんなに人が多いとは思わなかった十和田湖
今にも雨が降りそうな天候だが
陽も差しているので大丈夫だと思いたい
観光バスが多いが中国人が居ないので静かだ
ただ、ジジババの団体ツアー客が多かった
写真を撮る時にカメラの前に入り込んでくるので
図々しさは変わらないと思う。
乙女の像
.jpg)
.jpg)
.jpg)
駐車場から10分以上歩かないと到着しない
出来が悪いから一回捨てた作品だと言われている
高村光太郎作の乙女の像だ
外国の美術評論家にはそう言う意見の人が多いそうだが
日本では高名な作家の作品には誰も本当の考えは言いません。
と言う事でパッパと写真を撮って後にした。
奥入瀬渓流
.jpg)
.jpg)
今日は十和田湖を一周する予定である
奥入瀬渓流には今まで三回ほど来たことがあるが
十和田湖おいらせラインを走って終了していた
くねくねした道路だが所々駐車スペースがあるので
車を停めて見学することに困らない
紅葉の時期に来たことが無いので、その時は?
十和田湖おいらせライン
.jpg)
.jpg)
.jpg)
昼間は人が多いので出ることが無いと思うが
こんな所にもクマ注意の看板があった
最近あちこちで出るので勘弁してほしい
保護団体の圧力にいつまで屈しているのだ
何とかしないと観光客が来なくなるぞ!
政治家やVIPが襲われないと
何にもしない自治体ばかりだな
西十和田いで湯ライン
.jpg)
.jpg)
.jpg)
今晩の宿がある弘前方面に行くために
「西十和田いで湯ライン」をドライブする
いろんな十和田湖の顔が見えるが
こちらは道幅が狭いので観光客は全くいない
発荷峠から十和田湖を挟んで反対側にある
御鼻部山展望台から見ると雰囲気が違う
津軽藩「ねぷた村」
.jpg)
.jpg)
.jpg)
弘前市の「ねぷた村」を見学
初めてだと思ったが一度来たことがある
ねぷた村の入場料を払えば
駐車料金が無料になる事を思い出した。
ちなみに青森県にあるねぶた村は
弘前市、五所川原、青森市と三つある
知らないだけで他にもあるかも
弘前ねぷたの館
.jpg)
.jpg)
.jpg)
弘前城のそばにある「津軽」を丸ごと楽しめる
体験型観光施設の津軽藩「ねぷた村」に入る
実物大の弘前ねぷたが展示されているので
一年中祭りの熱気を体感できる
真っ先に津軽三味線を弾いている音が聞こえる
太鼓もたたけるが今回はパスした
揚げタコ等色々な物を造って実演している
今晩の宿
.jpg)
.jpg)
今晩泊まる宿がある弘前市に到着した
今回の旅行中に利用した中で
全く値段に合わないくらいひどかった
掲示してある料金が知らぬ間にか変わっていたし
サービスも悪くて夜中に何度も目が覚めた
まあ、二度と利用しないだけだが
七日目
.jpg)
.jpg)
五所川原市の「立佞武多の館」が
朝9時からのオープンの為に
時間調整を兼ねて岩木山に向けて出発
快晴の天気だ。(やはり持っている男だと思う)
津軽富士と言われているぐらいなので
多少雲が、かかっていても見栄えが良い
もう少しリンゴが赤く熟していればもっと映える
立佞武多の館
.jpg)
.jpg)
.jpg)
立佞武多の館には8時30分に到着した。
今回の旅で絶対見学したかった場所だが
早すぎたのでオープンするまで駐車場で待った
立佞武多の館は4階まで吹き抜けの展示室になっている
開店と同時に入館し目の前の立佞武多を見て
余りの大きさにびっくりシャックリ
※左の写真は大きさを比較の為にWEBより拝借
高さ23メートル
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
ねぶたの種類は地域によって三種類あり
それぞれ独自の形をしている
五所川原の立佞武多は高さが23mもあり現在三台ある
祭り本番の時には2,3,4階の通路が開いて
外に出陣する方式を取っている
※祭りは途中設計図を紛失して中断していたが
1998年に再開された。
五所川原広域農道(こめ米ロード)
.jpg)
.jpg)
五所川原広域農道(こめ米ロード)を走る
名前が示すように田んぼの中を
10Km以上ある真っすぐな道が続いている
シジミで有名な一三湖がある道の駅に到着
皆誰もがしじみラーメーンを食べている
当然のごとく自分も注文し食べた
出汁が効いた薄い塩味でとても美味かった
龍泊ライン
.jpg)
.jpg)
日本海を左に眺めながら龍泊ラインを走る
途中に中泊町で偶然見つけた七つ滝だパチリ
山岳からの清流が七段の断崖に落下して
滝を造り日本海に流れ込んでいる
ただ水量が少ないので真冬には凍るかも
素通りしていく車ばかりだった。
竜飛崎
.jpg)
.jpg)
.jpg)
眺瞰台(ちょうかんだい)からの景色が
ガス(雲)で全く見えなかったのが残念だが
山を越えたら快晴の青空と出会え
竜飛崎に着いた時には上天気になっていた
自衛隊のレーダーが設置されている場所からは
北海道の渡島半島がしっかり確認できたが
5月には逆に渡島半島から竜飛崎を見た。
津軽半島冬景色
.jpg)
.jpg)
.jpg)
石川さゆりのヒット曲「津軽半島冬景色」を聞く
歌が途切れることが無いくらい
訪れる人の全員が歌碑のボタンを押し楽しんでいる
近くには知る人ぞ知る階段国道があるが
誰も降りて行かないのは何故だ?
確かに草がボーボーと茂っているが
高野崎キャンプ場
.jpg)
.jpg)
この旅で初のキャンプをする予定で
高野崎キャンプ場に向かった
景色は良いし動物の被害もなさそうだ
テントを設営した後で
風が強かったのでペグを探したが見つからない
家に忘れてきてしまったのである。
慌ててホテルを予約したのは言うまでもない
青森市内
.jpg)
.jpg)
一時間ほどで青森市内に到着
今日は土曜日なので人も多かったし
何度も来たことが無いのに懐かしい気分だ
海風が爽やかに吹いて清々しい為に
家族連れやカップルが多く
楽しそうにブラブラ散歩していた。
ワ・ラッセ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
三種類ある「ねぶたの山車」の最後を見学
二回程行ったことがある
山の中にあった「ねぶたの里」が
いつの間にか無くなっていたので
新しく出来ていた「ワ・ラッセ」を見学した
ねぶたの里の方が祭り参加型だったが
こちらは見るだけなので雰囲気が違った。
山車
.jpg)
.jpg)
.jpg)
毎年新しいデザインの山車が出るので
本番の祭りをぜひ見たくなってきた
八月の初めから順番に祭事されるそうだが
ホテルを取るのに高そうだし苦労するだろうな
今まで大きいと思っていた山車だが
五所川原の山車を見た後では小さく見える
「ねぷた」と「ねぶた」
.jpg)
.jpg)
お祭りの呼び方で
弘前は「ねぷた」と言い
青森は「ねぶた」と云うと思っていた。
※ちなみに「ねぷた」と「ねぶた」と
呼び方が二つあるので聞いたところ
方言の違いで、どちらも正しいとのこと
今日まで間違って覚えていたのが少し恥かしい。
八日目
.jpg)
.jpg)
.jpg)
今日は下北半島を一周廻る予定である
まずは一度は行きたかった恐山を目指した
青森市内から120Kmほどあるので3時間コースだ
信号が無いので順調に走ることは出来るが
あちらこちらに「ツキノワグマ出没注意」の
掲示板があり近年の獣害の恐ろしさが解る。
三途の川
.jpg)
.jpg)
.jpg)
国道279号線の(むつはまなすライン)は
ハンドルを切ることが無いほど走りやすかったが
むつ恐山公園大畑線(県道4号線)に入って
恐山が近づくにつれて道が細くなって来た時
急に開けた場所に出たと思ったら
三途の川がある恐山入り口に到着した。
※柵がしてあるので渡ることが出来ない
恐山霊場
.jpg)
.jpg)
外輪山に囲まれた霊場は
外部からは見ることのできない途絶された場所。
三途の川にかけられた太鼓橋を渡って霊域に入ると
死後の世界のような風景が広がっている
行ったことが無いので解らないし
まだまだ後30年くらいは行く気が無い。
温泉風呂
.jpg)
.jpg)
恐山菩提寺の前には
参道を挟んで男女別の温泉風呂がある
男風呂を覗いたら先客がいたので
撮影OKの了解を頂き撮らせていただいた
見た感じ大変熱そうな湯の色をしていたので
入りたかったがやめた。
恐山菩提寺
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
比叡山・高野山とともに
日本三大霊山といわれる恐山
比叡山は行ったことがあるが記憶がない
「人は死ねば恐山に行く」と
言い伝えられてきが理由は知らない。
恐山菩提寺の前には仁王像が番をしている
地獄めぐり
.jpg)
.jpg)
.jpg)
石段を登ってゆくと地獄巡りの岩場がある
回りを見回すといくつかの地蔵が
広い岩場に点在しているのが見える
積み上げられた小石の上に風車
ぬいぐるみ、おもちゃ、その他日常品が
至るところに放置されているのは
奇妙な光景である。
極楽浜
.jpg)
.jpg)
なんだかんだと一時間ほど見学
地獄の次は天国の代名詞である極楽浜
硫黄の臭いが鼻につく宇曽利山湖が目の前
強酸性の為に生き物は住めないと言われるが
何故かウグイだけが生息している
何処が極楽かは人それぞれだと思うが
信じる者は救われるのである。
大間崎
.jpg)
.jpg)
寄り道してきたので家を出て8日かかったが
無事に本州最北端の大間崎に到着した。
高速を使わず下道のみだった為に1,650Kmだった
駐車場はたくさんあったが
人が少ないのにどこも満車だった
皆さん何処に行ったのだろう
一本釣りモニュメント
.jpg)
.jpg)
.jpg)
大間崎には何しに来たのだろう
考えたら来ることが目的で他には何もない
ただマグロの一本釣りのモニュメントと
一緒に写真が撮りかったし
最北端という言葉に魅了されているので
旅の目的は人それぞれなのと思う。
仏ヶ浦へ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
ナビを設定して仏ヶ浦へ向かった。
国道338号線はとんでもない道だった
間違いなく酷道と言っても良い
ツーリンマップでは普通に見えるが
くねくねしていて運転していても楽しくないし
景色を見る余裕は全くない。
そして駐車場に着いた時に又もクマ注意の看板が
海岸まで
.jpg)
.jpg)
.jpg)
海岸までの距離は、たったの600mだが
看板には「行きは20分帰りは帰りは40分」と注意書きが
速足で歩いたので10分少々で海岸まで降りた
目の前には海底から噴出した火山灰が押し固められ
自然が作り上げたとは思えない奇跡の造形美が現れた。
ただ、ここには船のツアーで来る事をお勧めする
何故なら帰りはハーハーぜーぜーを体験する事になるから。
仏ヶ浦駐車場へ
.jpg)
.jpg)
船で帰る人を横目で見ながら
覚悟を決めて駐車場に向かった
たった600mの距離だが階段に換算すると
1,000段くらいある気がする
心臓はバクバク、汗がダクダク出てくる
クマが怖いので二度と来るもんかと
大声を出しながら歩いた。
ホテルユニサイトむつ
.jpg)
.jpg)
今日の観光も無事終了して宿に向かう
「ホテルユニサイトむつ」は
築年数が経ってちょっと古いように見えたが
価格が安い割には室内は広くて良かった
駐車場は無料だったが徒歩3分と離れていたので
荷物を持ち込むのが大変だった。
それ以外はおおむね満足だったかな
九日目
.jpg)
.jpg)
.jpg)
朝7時30分とゆっくりスタート
雨が降っていたので気が重かったが
最初に本州の最果てと言われる尻屋崎へ行った
入り口に設置してある自動ゲートも目当てだった
何処にでもあるが観光地にあるのは珍しい
しかし行く所すべてにクマ注意の看板が
早く駆除しないと観光客が来なくなるぞ!
尻屋崎
.jpg)
.jpg)
.jpg)
灯台に到着したが誰も居ないし滅茶苦茶寒い
半ズボンとTシャツで来たことを後悔した。
真夏なのに寒々とした景色が意外と絵になる
残念なのは放牧されているはずの寒立馬が
何処にもいなかったことが悔しい
北海道の陸地も全く見えないので早々に立ち去った
道の駅「みさわ」
.jpg)
.jpg)
何処か見学する所ないかなと
スマフォ片手に地図とにらめっこしたが無い
鳥取砂丘より広い日本最大の猿ヶ森砂丘は
防衛省の管轄なので一般人は入ることが出来ない
三沢航空科学館は月曜日で休みなので
道の駅「みさわ」で時間をつぶした。
農耕馬のモニュメントがあったが意味は解らない
蕪島神社
.jpg)
.jpg)
.jpg)
昼前に早くも八戸市に到着してしまった。
宿をキャンセルしても勿体ない
さあ!どうする?
ウミネコの一大繁殖地の蕪島神社を見ーつけた
糞をかけられたらムカつくなと思ったが
8月にはヒナが巣立った後なので全くいなかった。
なんて日だ!!
葦毛崎展望台
.jpg)
.jpg)
.jpg)
蕪島神社の下にあった休憩所で散策マップを頂き
他の雄観光地の情報を聞いた
この辺は種種海岸なので景勝地が多い
ぐるっと一周してきても面白いと言われた
まずは一番近い葦毛崎展望台に寄った
ただ、後も同じような景色なので途中で止めた。
八戸グランドホテル
.jpg)
.jpg)
宿泊施設に向かったが時間が早すぎたので
近くにあったドンキで時間をつぶした
滅茶苦茶大きな規模なので有難かった
ここで不足したものや食料を仕入れホテルへ
建物は新しくないが清潔感があって良かった
朝食バイキングも品そろえが多く美味しかった。
十日目
.jpg)
.jpg)
.jpg)
今日は2011年に起きた東日本大震災の復興現場を
二ヶ所見学する予定で朝7時10分に宿を出発した。
まずは無料の三陸沿岸道に乗り二時間程(100km)走り
鵜の巣断崖(リアス式海岸絶景)を見に行った
駐車場に到着した時には誰もいないし
お馴染みのクマ出没の注意書きの横には
国土強靭化対策工事中の看板には中止の文字が(怖)
鵜の巣断崖
.jpg)
.jpg)
.jpg)
断崖まで大きな音で歌を聴き鈴を鳴らし
廻りをキョロキョロしながら10分程歩いた
散策道は綺麗に整備されてはいるが
今までにクマが出たのだろうと思うと恐い
断崖が視界に入る所まで来るとひと安心
ただ、ユーチューブで見た時ほど
綺麗な景色だと思わなかった。
龍泉洞
.jpg)
.jpg)
次は内陸まで一時間弱走って龍泉洞へ
大昔に一度来たことがあるので想像はつくが
7月の大雨の影響で再オープンしたばかりだった
チケット売り場で地底湖が濁っていると聞き
疑心暗鬼で洞窟へ入った第一声が
奥から吹いてくる冷気であ〜涼しいだった。
洞窟へ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
体感温度は摂氏18度くらいでちょうど良いが
水がぽたぽたと垂れてくるので冷やっこい
奥に進むと「亀岩」なる物があった
無理に見れば亀に見えなくもないが怪しい
写真では全く想像できない
鍾乳石で出来た洞穴ビーナスと書いてある
卑猥な名前の岩もあった(笑)
地底湖
.jpg)
.jpg)
.jpg)
地底湖を見るには洞窟内にある階段を
120段登り100段降りると書いてあったので
年齢が高い方たちはショートカットしていった
地底湖の水はカルシウムを含んでいるので
少し濁っているように見える
第三地底湖は深さが98mあるそうだ。
川の流れに
.jpg)
.jpg)
.jpg)
洞窟内は高さが低く狭いし結構滑るので
頭や体のあちこちをぶつけながら退場した
外に出ると湧き水が飲める場所があったが
想像していたほど冷たくは無かった。
洞窟から出て来た水が
しぶきを揚げて川に流れ出てたけど
この水は濁りが無くて綺麗だった。
震災遺構
.jpg)
.jpg)
.jpg)
三陸海岸の田老まで走り
東日本大震災で高さ17mを超える津波の被害を受け
4階まで浸水、2階までは柱を残して流失したものの
倒壊することなく留まった「たろう観光ホテル」
震災遺構として残してあるので想像しながら見学した
あの高さまで押し寄せた津波の恐ろしさは
テレビでしか見たことが無かったのでショックだ。
田老防潮堤
.jpg)
.jpg)
.jpg)
明治三陸大津波(1896年)と三陸大津波(昭和8年)の
過去二度も壊滅的な被害を受けた田老地区
町全体を囲む総延長2,433メートル高さ10メートルの
長大な防潮堤は昭和54年に整備が完了した。
だが、2011年(平成23年)3月11日に発生した
東日本大震災による津波は、この防潮堤を超え
田老の町を飲み込み甚大な被害を及ぼした。
浄土ヶ浜ビジターセンター
.jpg)
.jpg)
気分を変えて近くの浄土ヶ浜でリフレッシュ
マイカー禁止なので第一駐車場に車を停め
土、日、祝日ならビジターセンターから
砂浜まで無料の連絡バスが出ているが
ウイークデーの為15分くらいかけて浜まで歩いた
人気の景勝地なので中国語が氾濫していた。
浄土ヶ浜
.jpg)
.jpg)
.jpg)
三陸海岸きっての白い岩肌の名勝地である
ここも震災の影響で被害を受けたはずだが
その感じが全くない
何でだろう?
想像だが住んでいる人が居なかったのが
関係しているかもね
時間がもっとあれば泳ぎたいぐらいだ。
陸前高田ユースホステル
.jpg)
.jpg)
.jpg)
今日の見学地の中で一番行きたかった陸前高田へ
浄土ヶ浜からは120km以上あるので3時間弱かかるが
何といっても無料の三陸自動車道がある
WEBで調べたら道の駅「高田松原」に車を置いて
被災地復興跡を見学するようにと
出ていたのでナビを合わせて向かった。
奇跡の一本松
.jpg)
.jpg)
.jpg)
今までテレビでしか見たことが無かった
「奇跡の一本松」を念願かなって見学出来た
駐車場を出て廻りをぐるりと見渡すと
遠くから見ても存在が一本だけ確認できる
お参りを兼ねて見るには10分ほど歩くことになる
未来永劫に残すためにコンクリートで出来ているが
何か言いたい事があるかのように感じた。
献花台
.jpg)
.jpg)
.jpg)
一輪の菊が供えられた献花台から見ていると
あれだけの大津波が来たことが
信じられないほど穏やかな海が広がっている
しばらく眺めていたが何故か涙が出て来た。
震災を忘れない様に語り部さんもいたし
団体旅行客も多く訪れていた
全国の人も一度は来るべき場所だと思う
東日本大震災津波伝承館
.jpg)
.jpg)
.jpg)
東日本大震災津波伝承館には
時間が許す限り見学させていただいた。
ビデオを見ると震災当時のことがよくわかる
震災前、震災後の街の様子も映像で見ることができ
一瞬で生活を奪った津波の恐ろしさを思い知った。
感想は、ただただ言葉が出なかった
自分がその場に居たら同じ行動できただろうか
ホテルルートイン気仙沼
.jpg)
.jpg)
急遽予約したホテルルートイン気仙沼
お得感たっぷりの値段で部屋は綺麗で広い
風呂も大きかったので、ゆっくりと浸かれた
何と、あの価格で朝食も付いていたし
種類も多くて大変美味かった
単なるビジネスホテルと思っていたので
待遇の良さに何度も泊まりたくなった。
十一日目
.jpg)
.jpg)
曇り空の中、朝7時15分出発した
前夜ホテルで蔵王までの行き方を調べたが
仙台市内の渋滞を避けるのが優先だったので
一度内陸方面に向かってから南下した。
天候は雨予報なので景色は期待してなかった
高速道路を使わない旅と決めていたので
蔵王エコーラインまで4時間かかった。
蔵王御釜
.jpg)
.jpg)
.jpg)
宮城県側から蔵王エコーラインに入った為に
ヘアピンカーブの連続でガスもかかり
なおかつ前を大型観光バスが走っていたので
追い越し出来ずチンタラ走った。
ハイラインの駐車場に到着した時には
ガスも取れて御釜がしっかり見えたのは
やはり持っている男だ!という感じかな(笑)
今まで三度来たが三回ともしっかり見えた。
蔵王エコーライン
.jpg)
.jpg)
.jpg)
山形県は蔵王以外に何がある?と言いたい
時計を見れば午後1時前である
このまま麓まで降りて少し考えていたら
蔵王スキー場が見えた
昔からモンスター樹氷を見たかったので
一度はスキーに来たかったが
未だに念願はかなってない。
道の駅「やまがた蔵王」
.jpg)
.jpg)
米沢市に宿を取っているので
行くところが無く時間が余ってしょうがない
以前行った事がある天童市の将棋資料館を見学するか
月山湖へ行って高さ112mの大噴水を見るか
結局途中まで行ったがあきらめて
道の駅「やまがた蔵王」で時間調整した。
せっかく山形まで来たのに何やってんだろう!
ビジネスホテル平成
.jpg)
.jpg)
一時間ほどかけて米沢市の宿泊ホテル平成へ
ビジネスホテルだが朝食付きで予約した
年季が入っているが値段もお得だし
寝るだけなので何も問題はない
早速ビールを飲みながら観光地を探す
結構近くに興味がある所があったが
酔っぱらっていたので明日行く事にした。
十二日目
.jpg)
.jpg)
.jpg)
朝7時30分
昨日調べていた上杉神社へ行く
ホテルを出て5分で到着した
開館前だったので当然誰もいないし
拝観料(700円)も取られなかった。
参拝するまではローカルな神社だと思っていたが
想像以上に立派な神社だった。
上杉神社
.jpg)
.jpg)
.jpg)
戦国最強の武将と語り継がれている
上杉謙信を祭神として
米沢城本丸跡に建立された上杉神社。
上杉謙信にあやかって開運招福や諸願成就
さらには学業成就や商売繁盛の
ご利益もあるとされるパワースポット
※俺は戦国最強は武田信玄だと思う
道の駅「喜多の郷」
.jpg)
.jpg)
福島県の会津若松まで南下し
17年前に東北を旅した時の初日に
車中泊した場所、道の駅「喜多の郷」に着いた
記憶をさかのぼれば涼しいと思っていたが
ものすごく暑くて温泉に入浴後
併設されている食堂で
最後まで涼んでいたことを思い出した。
飯盛山
.jpg)
.jpg)
.jpg)
白虎隊自刃の地である飯盛山へ
汗をダクダクかいてフーフー言いながら登った
横にはエスカレータがあるが乗らないのだ
確か250円徴収される
駐車料金を千円も払うのだから無料にすれば良い
観光地とはいえ、ちょっとあくどい
※地図は飯盛山から鶴ヶ城までの位置
白虎隊
.jpg)
.jpg)
白虎隊(びゃっこたい)とは
戊辰戦争のとき
会津藩士の子弟によって編成された少年隊で
主に16、17歳の青年によって組織された部隊
会津藩は年齢毎にそういった
部隊(玄武・青龍・朱雀・白虎)があった。
1868(明治元年)8月に
明治政府軍と戦ったがやぶれた。
白虎隊自刃の地
.jpg)
.jpg)
.jpg)
悲劇として知られるのは二番隊の事
彼らは戦場の混乱の中で
指揮をしていた隊長とはぐれ
飯盛山に辿り着いたが
そこで燃える城下町を見て
この戦争は負けと判断して自刃した。
鶴ヶ城へ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
白虎隊が燃えていると勘違いした鶴ヶ城へ
飯盛山から車で10分もあれば到着する
お城なので仕方がないが
駐車場から天守閣まで10分以上歩くことになる
歴史に疎く失礼ながら今まで焼失して
城址公園として残っているもんだと思っていた。
あ〜恥ずかしい
鶴ヶ城天守閣
.jpg)
.jpg)
.jpg)
福島県会津若松市のシンボル鶴ヶ城
約630年前に作られ正式には若松城と言う。
1868年に起こった戊辰戦争の際には
新政府軍の猛攻に耐えた
難攻不落の城としても有名で
赤瓦の5層の天守閣がとても美しい。
日本百名城の一つである
日光へ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
早いもので栃木県まで戻ってきた
日本海側から青森県の最北端まで8日間かけて行き
太平洋側から4日間でここまで下りて来たが
会津若松から日光まで二時間かかった
国道121号線は結構険しい道だったが
市内に入ると平日なのに観光客が多かった。
神厩舎
.jpg)
.jpg)
.jpg)
今まで一度も来たことが無かった日光東照宮へ
駐車場に停まっている車のナンバーを見ると
全国津々浦々から参拝に来ていて驚いた。
入場料1,600円也を払い門をくぐると
さっそく人垣が出来ていたのが
「見ざる、言わざる、聞かざる」の
三猿や「招き猫」の神厩舎だった。
日光東照宮「陽明門」
.jpg)
.jpg)
.jpg)
愛知県三河にある松平家の先祖や家康の生家
そして静岡の久能山東照宮は行った事があるが
日光東照宮には来たことが無かった
金箔(?)をふんだんに使った東照宮
凄いとしか言いようがないが
一度は拝みたかったので満足である
ただ、第一印象は派手だな〜
随身像(ずいじん)
.jpg)
.jpg)
平安時代以降に
貴人の外出時に警衛と威儀を兼ねて
勅宣によってつけられた近衛府の官人
解りやすく言うと門番かな
しかし何処を見渡しても金箔だらけ
そりゃ門番は要るわな〜
はははは
若松エクセルホテル
.jpg)
.jpg)
.jpg)
新築朝食付きで4,500円さらに専用駐車場付
最後の一部屋の言葉に慌てて予約した
群馬県伊勢崎市の若松エクセルホテルへ向かった。
街中なので車が多く結構時間がかかったし
土地勘が全く無いので参った。
しかも次の日の朝出発時に
通勤ラッシュで大渋滞に合いイライラが倍増
十三日目
.jpg)
.jpg)
.jpg)
台風が来ると各局がニュースで脅していた
数日前から毎日頻繁に話題にしていたが
これまで全く影響が無く上天気が続いていた
さすがに少し不安になり今日中に家に帰ることにした
道の駅「しもにた」をナビに設定して出発したが
あちこち渋滞していて進行方向が次々と変わり
結局、伊勢崎市を大回りして目的地に到着した。
長野県
.jpg)
.jpg)
.jpg)
佐久市に入ると青空が広がってきた。
本当ならもう一日長野県北部を観光して
帰るつもりだったが仕方ない
蓼科を少しだけ観光して家路についた
結局この日も家に着くまで快晴で
一日損した気分になった。
マスコミも狼少年にならない様に注意しろ!
旅行後記
.jpg)
.jpg)
.jpg)
今回の行き当たりばったりの東北の旅
本州最北端の地や東日本大震災の被災地の現状を
自分の目で確かめたかったので良い経験をした。
又、今回は高速道路を使わずに東北を一周したので
全走行距離は3,100Kmと予想通りだったが
長野県と山形県はガソリン価格がめちゃ高かった
総費用は宿泊と食事代含めて14万円だった。