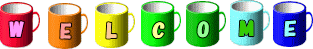
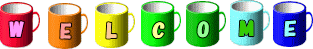

|
|




|
|
初日
.jpg)
.jpg)
.jpg)
国道150線沿いの海岸では
サーフィンをしている人が多かったが
御前崎灯台の駐車場には
我が家の車だけしか停まってなかった。
海岸には静岡県最南端岬の看板が建っていて
写真を撮るには誰にも邪魔されずに済んだが
肝心の灯台は近くで見るとみすぼらしかった。
浜岡原子力館
.jpg)
.jpg)
.jpg)
御前崎灯台から少し戻ったところに
中部電力の浜岡原子力館があったので
暇つぶしに寄ってみた。
ここは無料で遊べる施設が豊富で
原子力発電の仕組みを勉強するには良いし
意外と楽しめた。
静岡名産
.jpg)
.jpg)
静岡といえば、お茶がすぐ浮かんだ。
御前崎を後にすると一面の茶畑が広がっていたが
綺麗に刈り込みがしてあるので一度上空から見たい気がする。
昼ごはんは景色のすばらしい川沿いで食べたが
キャンプに適しているので夏休みになったら来たいと思った。
(アブがいるかも知れないが)
大井川鉄道
.jpg)
.jpg)
.jpg)
大井川鉄道は国道473号と平行して走っているので
車を止めて写真を撮るには良い場所が所々ある。
川沿いには駐車場もあり
一眼レフカメラを構えたマニアが多くいた。
鉄道マニアでは無い自分だがカメラには興味があるので
良い被写体を求めて一緒に待ち構えていた。
千頭駅
.jpg)
.jpg)
.jpg)
大井川鉄道の千頭駅はSL列車の出発(終着)駅である。
列車が到着すると入場券を買ってホームに入れるので
SLに乗らなくても記念写真を撮ることが出来る
又、SLには乗るのが良いのか見るほうがいいのかと云えば
自分は見る方がいい。
道の駅
.jpg)
.jpg)
千頭駅の隣に併設されている道の駅「音戯の郷」は
音と戯れることをテーマとした体験ミュージアムである
280インチの大画面スクリーンでの迫力ある映像を体験したり
展示されている色々な物から音が出たりして結構楽しめた
水道の蛇口をひねると低音の音が出て子供達は大喜びだった。
寸又峡
.jpg)
.jpg)
.jpg)
南アルプスの山並みが眼前に迫る秘境奥大井「寸又峡」に到着。
夢のつり橋に行くには寸又峡の温泉街に車を停め遊歩道を歩く。
寸又峡プロムナードコースと名付けられた道は舗装されており
入口には一般車両の進入を禁止するゲートが設置されているので
車を気にせずのんびりと散策することが出来た。
夢のつり橋
.jpg)
.jpg)
.jpg)
駐車場から20分程散歩したところで夢のつり橋に着いた。
大間ダム湖にかかる夢のつり橋は「長さ90m 高さ8m」である。
渡れる人数に限りがあり混んでいる場合は待つことになるが
偶然にも誰もいなかったので渡りだした。
が・・・下が丸見えなので怖くて金ちゃんがキュイーンときた。
川根温泉
.jpg)
.jpg)
.jpg)
途中のコンビニで食料を仕入れた後で
道の駅「川根温泉」に到着した。
駐車場からはSLも見えるし(列車は来なかったが)
名前のとおり温泉も併設されているので
温泉に入った。(疲れを取るには温泉が一番)
夜になると車中泊している人が多くいたので
今晩は安心してここで寝ることにした。
二日目
.jpg)
.jpg)
.jpg)
鳳来寺は徳川家康を祀る神社である。
徳川三代将軍家光が日光東照宮に参拝された時に
「松平広忠が立派な後継ぎを得たいと思い
奥方と共に鳳来寺にこもり祈願して生まれた子供が
家康公であった」と書いてあった事を読んで
ここに東照宮を建築しようと決心されたそうだ。
寝覚ノ床
.jpg)
.jpg)
.jpg)
大井川から半日以上かかって
国道19号線沿いにある寝覚の床に到着した。
スキーに行く時に何度も横を走っていたが
今まで見学したことが無かったので今回初めて寄った。
此処は浦島太郎の伝説があり
亀を助けて竜宮城へ行った話は広く知られているそうだ。
俺は全く知らなかったが・・・
浦島太郎伝説
.jpg)
.jpg)
故郷に帰った太郎が誰一人知る者がなく淋しさに耐えかねて旅に出て
たまたまこの美しい里の景色が気に入り住み着いたが
竜宮の生活が忘れられず乙姫様に貰った玉手箱を再び開けると白髪の翁となった。
今までのことは夢であったかと言うことからこの里を寝覚めと言い
床を敷いたような岩を見て「寝覚ノ床」と呼ぶ様になったという逸話がある。
奈川渡ダム
.jpg)
.jpg)
.jpg)
国道19号の薮原を左折して乗鞍に向かうと
松本方面から来る国道158号と交差する所に
奈川渡ダムがある
観光ダムではないが駐車場も整備されており
ダムの上から下を覗くと
男なら解るが金ちゃんがスッとする(笑)。
乗鞍岳
.jpg)
.jpg)
乗鞍岳は岐阜県と長野県にまたがっており
長野県側のふもとには乗鞍高原が広がっている。
名称は姿が馬の鞍に似ている事から名付けられた。
本州の太平洋側(木曽川)と
日本海側(信濃川、神通川)の中央分水界が剣ヶ峰を通っている。
又、スキー場もあり標高が高くて雪質も良くコースもバラエティーだ。
温泉も有名で源泉は酸度の強い乳白色であり近くに白骨温泉がある
乗鞍岳中腹にある湯川源泉から温泉地まで引湯している。
遊歩道
.jpg)
.jpg)
善五郎の滝は乗鞍三名滝の一つで
乗鞍高原の中ほどにあり比較的簡単に行くことができる。
滝へ行くのに最も近いのは乗鞍スーパー林道を三本滝方面へ向かい
林道沿いにある駐車場に車を停め道路を横断して
アップダウンの激しい遊歩道を約15分程歩けば展望台に着く。
靴はスニーカーが適しているが中にはハイヒールで来た人もいた。
善五郎の滝
.jpg)
.jpg)
.jpg)
善五郎の滝は森が開けた部分にあるため
遠くからでも姿を見ることができる
ここからは乗鞍岳と善五郎の滝を一望することができ
雄大な乗鞍の景色を満喫出来る。
三本滝にも行ったが
熊が出たと看板が掲げてあったので
怖いので止めて番所大滝も見学せずに
沢度の駐車場まで行って寝た。
沢度駐車場
.jpg)
.jpg)
.jpg)
上高地へ行くには公共交通機関でしかないので
マイカーで行く場合には
岐阜県の平湯か長野県の沢渡(さわんど)に
乗用車を置くことになる
両駐車場共最盛期にはすぐ満車になるが
上高地で一日中過ごす人は少ない?と思うので
タイミング良ければ昼過ぎには駐車出来ると思う。
三日目
.jpg)
.jpg)
.jpg)
市営沢度駐車場を出発して上高地に向かった。
各駐車場を経由して観光客を乗せたがすぐに満員になった
バスで行く場合は
大正池で降りて散策しながら河童橋に行くのが良い
逆の場合には帰りのバスが満員の時が多くて
大正池で乗車することが困難の為だ。
バスは次々とやって来たが
ここで降りる人は意外と少なかった。
大正池
.jpg)
.jpg)
.jpg)
バスを降りて思いっきり深呼吸したら実に空気が旨かった。
ここから3時間程かけてバスターミナルまで散策していく予定だ
1915年6月6日に焼岳の大爆発で
膨大な溶岩流により梓川をせき止められ
短時間のうちに川の水は上高地温泉まで達し大正池の誕生となった。
水没した幻想的な立ち枯れの木が幹だけ残っているのが情緒を誘う。
焼岳
.jpg)
.jpg)
.jpg)
焼岳の写真は大正池と
少し歩いたところにある千丈沢から撮った。
標高は2,455mで
長野県と岐阜県の飛騨山脈の主稜線上にある。
※右側の写真は300ミリ望遠レンズにて撮影。
遊歩道
.jpg)
.jpg)
.jpg)
ビジターセンター方面へ歩いて行くとサルと出会った。
サルはとても賢くて
睨み付けた自分には何もしてこなかったが
ビビッていた子供たちには威嚇してきた。
※後で知った事だがサルはじっと見ていると
「ケンカ売っとんのか?」と思わっているらしいので
本当は睨みつけてはダメだそうだ。
田代池
.jpg)
.jpg)
田代池は大正池とともに
大正時代に焼岳の噴火により流れ出た溶岩が
千丈沢をせき止めたことでできた浅い池で
周囲は湿原になっている。
水面に北アルプスの山並みが映るほど水の透明度が高く
イワナなどの川魚が生息している。
河童橋
.jpg)
.jpg)
.jpg)
上高地は大正池から横尾までの
前後約10km、幅最大約1kmの堆積平野である。
上高地全体を観光するには半日では足らないと思うので
余裕を持って出かけることを勧める。
観光名所の河童橋を背にして
お気に入りの写真を撮るには苦労するが遠景の場合は問題ない。
また穂高連邦の向こう側は
岐阜県の奥飛騨温泉郷で新穂高ロープウェイがある。
梓川
.jpg)
.jpg)
.jpg)
梓川に沿って上高地バスターミナルまで散策した。
マイナスイオンたっぷりの空気を吸いながら
所々で休憩して写真を撮った。
ゆっくりと散策したがマナーを守っている人が多く
歩き煙草をしている人はいなかった。
写真は河童橋を挟んで前後から撮ったが
雰囲気は全く違った。
上高地バスターミナル
.jpg)
.jpg)
.jpg)
天気が良かったので上高地でゆっくり過ごした。
日程にゆとりがあれば明神池まで行きたかったが
時間が無くてあきらめた
次に来るときには明神池を見学したい
午後二時を少し過ぎた中途半端な時間なので
沢度駐車場行きのバスは空いていた。
平湯温泉
.jpg)
.jpg)
.jpg)
温泉に入るため平湯に向かった。
1997年に開通した安房トンネルのおかげで
岐阜県側に行くには便利になった。
平湯ターミナルにある温泉は満員だった為
少し離れた所のひなびた温泉に入った
温泉代は安かったが露天風呂だけだったので
女性には辛い場所かも知れない。
奥飛騨温泉郷
.jpg)
.jpg)
.jpg)
道の駅「奥飛騨温泉郷上宝村」に午後5時に着いたが
駐車場がいっぱいだったので時間をずらして再度行った。
車中泊恒例の「すがきや味噌煮込みうどん」と
絶対、欠かすことのないビール(発泡酒)で乾杯した。
が・・・酔っ払っていた為に車のキーを紛失して慌てたが
予備の鍵を持っていて助かった。(ふ〜助かった)
四日目
.jpg)
.jpg)
.jpg)
朝市を見たくて高山に行ったが
駐車場が満車の為しばらく待たされた
朝市が開催されている場所まで慌てて行ったが
想像していたよりも質素な朝市だったので
ガッカリした。
高山市内
.jpg)
.jpg)
.jpg)
陣屋前で写真を撮っている人が多かったが
意味は全く知らなかった。
陣屋とは江戸時代に郡代・代官が治政を行った場所で
御役所や郡代(代官)役宅、御蔵などの総称である。
幕末には全国に60数ヵ所あった郡代・代官所の中で
当時の建物が残っているのはこの高山陣屋だけである。
平湯の滝
.jpg)
.jpg)
.jpg)
平湯の滝はゆっくり見た事が無いので
わざわざ高山から戻ってきた。
国道158号はスキーや観光で何度も通っていたが
一度だけ見学したことがあるだけで素通りが多かった。
滝の廻りは5月でも雪が残っていたが
冬になると滝ごと凍って
夜にはライトアップもされるというので
真冬になったら再度来ようと思う。