平成27年度の実施事項記録
1. このページは4月から記載を始めます。先ず、昨年平成26年3月に市から配られた「防災マップ」を是非ご覧ください。
参考までに要約を下に掲載します。
 |
全家庭に配られました。
災害用伝言ダイヤルの使用方法など参考になります。
家族でしっかり見て下さい。 |
| 避難場所です。状況にもよるが、自主防災会の指示に従いましょう。 |
 |
 |
我々の所は震度6強の所にあります。
固定してない家具の大半が移動・転倒し、補強されていないブロック塀がたおれる。古い木造住宅は傾いたり倒れるものもある。
揺れは数分間続くと予想される。 |
| 我々の所は残念ながら可能性中の所にあたります。 |
 |
 |
被害予想です。多いとみるか少ないとみるか?
液状化では家が傾くが倒壊はしない。震度6強だとよ古い家で構造上問題のある場合は倒壊の恐れもあるが、大部分は全倒壊はしないと思われる。
①自宅の安全な場所を決めておく ②寝室の転倒物は固定する 事が必須である。 |
政府がネットで公表している地域別被害状況予測 も参考になります。
2.平成27年3月15日(日)町内会期末総会が行われ、続いて「自主防災会総会」も行われました。関係資料は町内会回覧で通知しました。
周知のことと思いますが、町内会の全員が「自主防災会」に所属されています。
3.平成27年4月11日(土)自主防災会議が開催され、27年度の活動計画などの検討を行いました。
4.平成27年4月19日(日)町内会班長会議が開催され、同席で会長・副会長出席で「自主防災会の27年度活動方針などを」報告ました。関係書類は町内回覧されました。
5.平成27年4月19日付で「吉池団地」専用の住民簿(防災会台帳:災害時の要援護者把握を目的とする。)作成依頼が町内回覧さ れました。この台帳はプライバシーに配慮して自主防災会会長と副会長専用で外部に漏れない仕組みになっつています。
6.平成27年4月25日:冒頭に記載の通りネパールの首都カトマンズを含め巨大地震が発生。甚大な被害となっています。
7.平成27年5月29日:冒頭に記載の通り 口永良部島でマグマ噴火。島民は屋久島へ避難。
8.平成27年5月30日:冒頭に記載の通り 小笠原諸島西方沖の深度682km(太平洋プレート内部)でM8.1の地震発生。
9.平成27年5月、先にお願いした災害時の要支援者把握のための住民台帳が副会長の所へ通達されました。
10.夏の防災訓練については町内会回覧でお知らせされました。
11.平成27年7月12日(日):午前10時~10時50分、東児童遊園地で「町内会・防災訓練」が実施されました。
町内会の役員・班長さんをはじめ若手の参加もあり、消防署のご指導の下、熱心に消火訓練と立ち上がり消火栓の取扱い訓練が行はれました。
各家庭の「消火器」の対応年数や外観を見て、必要に応じて交換してください。
 |
 |
12.8月1日 市の広報と一緒に「巨大地震に備えて」との冊子が各ご家庭に配られました。よくまとまっていますのでご家族でご 覧ください。
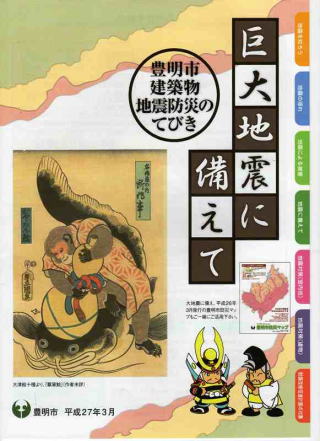
13.吉池区防災訓練のお知らせ(町内回覧)
平成27年9月13日(日)午前8時30分~11時00分(雨天中止)
中央公園
350人分の炊出し、防火訓練、自転車の乗り方指導、訓練防災機材取扱い
参加希望者は町内会長または副会長へ申し出て下さい。
14.7月29日 防災会用「町内地図」作成。
15.平成27年9月13日(日)の「吉池区防災訓練」が中央公園で行われました。
午前8時30分から4グループに分かれ、4項目の訓練を行いました。
1.)自転車の正しい乗り方。2.)防災機器(ハソリの使い方・発電機の使い方・簡易トイレの作り方)の取扱い訓練。3)立ち上がり消火栓の使用方法訓練。4.)家庭にある消火器の取扱い方訓練と煙感知器、熱感知器の点検方法の講義。

自転車の乗り方訓練・法律を守りましょう。
|

発電機などの取扱い訓練 |

立ち上がり消火栓。ホースの繋ぎ方訓練
|
 。 。
家庭にある消火器。粉末の出るのは15秒間。8年くらい
での交換が望ましい。底の錆ているものは危険。
|
婦人会の方が非常食の炊出しをして、訓練参加者に配られました。以上
16.これから暖房を使う時候になります。くれくれも火の用心。煙感知器や
感知器のテストをしてください。

2階の階段上に取り付けてある煙感知器の事例。
ボタンを押して鳴ればOK
|

台所に付けてある熱感知器の事例。
これは紐を引っ張って鳴ればOK |
購入時の説明書をご覧ください。ボタンを押すものと紐を引くものが一般的なものです。
17.平成27年10月6日(火)社協で「東日本大震災応援体験談」を聴取しました。
元豊明市の職員で、平成25年から2年間と平成27年4月から3か月間「宮城県岩沼市」へ応援派遣をされた山田 啓二 氏の体験談を聴講しました。
①取り壊し家屋の確認②被災程度の判定③被災者生活支援④各種補助金申請⑤仮設住宅建設⑥集団移転計画・・・。
災害後の復興がいかに大変なことが分かりました。復興には地域の結びつきの大切さも実感できました。

18.平成27年11月15日(日)防災講演会
文化会館で「東日本大震災」の復興に尽力された吉田亮一 氏の講演を聴取しました。学校での避難生活の大変さを実感するとともに、リーダーの力量が必要なことが分かりました。
特に避難所などで「中学生が新聞を壁に貼ったり」「高校生がポリタンクで水を運んだり」活躍するのを聴いて、自主防災会も中学、高校生をも巻き込んだ活動にできればよいなーと感じました。
アトラクション的に、名古屋短期大学生が被災地慰問」で行っている寸劇の公演がありました。本グループは後日新聞で紹介されていました。
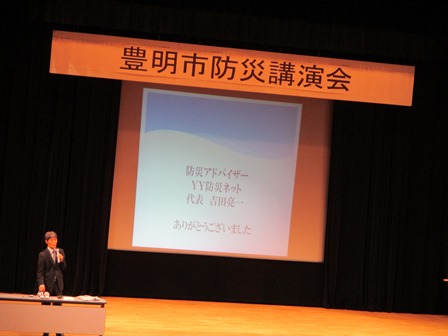
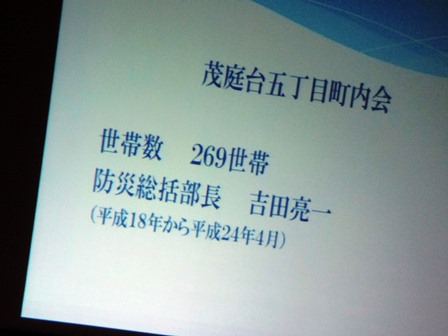
19.平成27年12月12日(土)情報伝達・救急救命訓練
東児童遊園地で行われました。今回は藤田保健衛生大学の羽田教授においでいただき、AEDの正しい使い方をはじめ、ゴミ袋で作る防寒着、雨カッパの作り方、正しい「三角巾」の取扱いについてご指導いただきました。
 |
4か所にAEDの訓練場所
を設けました。 |
AEDの取扱い訓練。
皆さん熱心に取り組みました。
ここの防災会の方は取扱いが上手とのお褒めがありました。 |
 |
 |
ゴミ袋を部分的に鋏で切って、防寒チョッキ
と雨合羽の作り方を教わった。 |
三角巾の使い方訓練。
なかなか難しい。新しい三角巾が贈られたので、
自宅で練習してください。 |
 |
情報伝達訓練の結果
伝達率:88.3% 黄色い布不掲出:30戸(16.7%) 参加者:約50名(内、町内会班長17名)
20.平成28年1月10日 中央公園での消防出初式に出席しました。
21.平成28年2月7日、自主防災会役員会を開催しました。
22.平成28年2月21日、防災倉庫の清掃と点検をしました。
平成28年度(4月から)このページは平成28年度のお知らせ・報告に変更します。
トップページに戻る
次のページへ





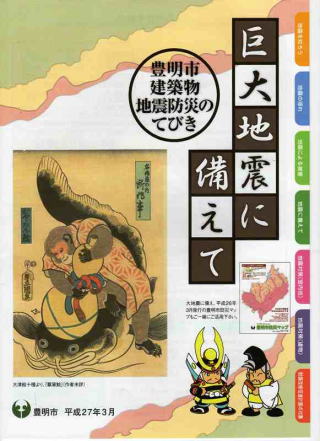



 。
。
