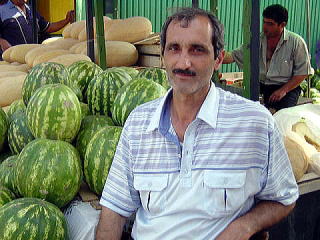|
宿泊先 ホテル名 ロシアホテル <3★5500室> 【住所】VARVARKA STRRET 6, MOSCOW, RUSSIA 【連絡先】TEL:095) 2326254 FAX:095) 2326248 【ホテル紹介】赤の広場とモスクワ川に面し、聖ワシリー寺院の近くに位置するスターリン時代の高層建造物。政府機関の集まる地域を見渡せる。規模にかけては、世界でも指折りのホテル。21階建て、10月革命50周年を記念して建てられた。 私たちは、9階の184番の部屋、バス・トイレ・冷蔵庫・テレビ等は異常なし。セーフティボックスの設備なし。9階の北側のおばさんに部屋の鍵を管理された。ゴキブリ・蚊も現れたホテル。 |
 早朝赤の広場まで散歩に出かける。ホテルの周囲を一周するだけで、15分かかった。 |